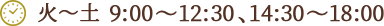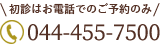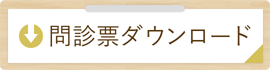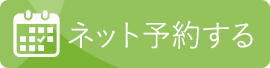公開日 2025.8.21
特徴・作用
メラトベルは、生体内で産生されるホルモンである、メラトニンを医薬品として合成した薬で、睡眠を促し、体内時計を調整する作用をもっています。
メラトニンは、米国等ではサプリメントで購入可能ですが、日本ではできません。
医薬品として、ノーベルファーマ社により開発され、2020年に承認されました。
メラトベルは、視床下部のメラトニンMT1受容体とMT2受容体に作用します。
メラトニンは、MTI受容体で睡眠を促し、MT2受容体で体内時計を調整するとされています1)、2)、(図1)。
図1 メラトニン(メラトベル)の作用機序
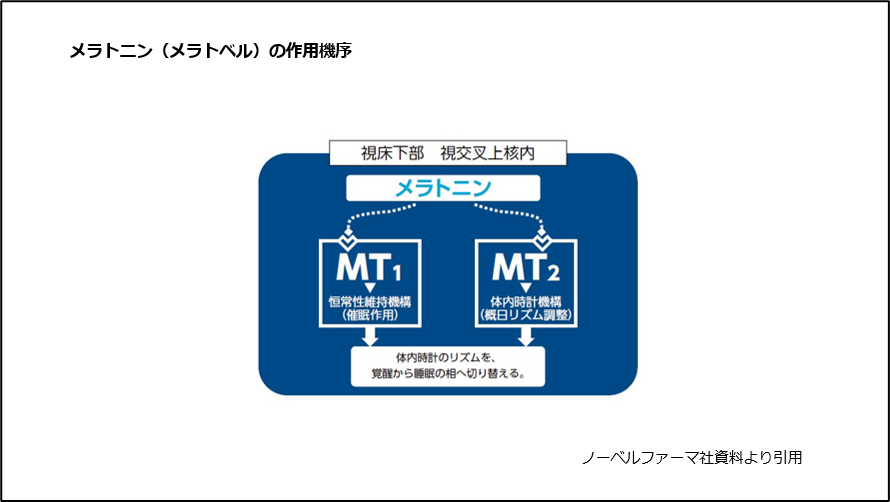
ラメルテオン(ロゼレム)も同じ働きですが、作用の強さに大きな違いがあります3)、4)。
ロゼレムの方が作用が強く、メラトベルの方が作用がおだやかです3)、4)、(図2)。
図2 ロゼレムとメラトベルの作用の強さの比較
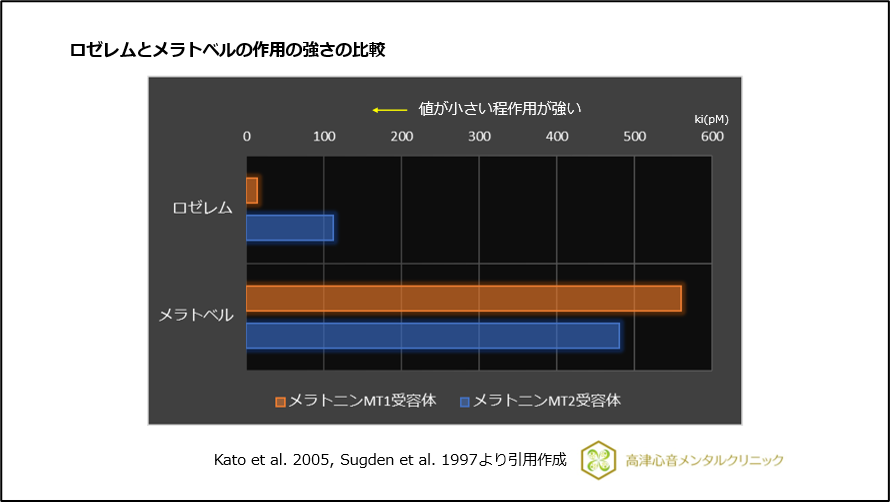
メラトベルは小児の神経発達症への適応のため、この強さが適量であるといえます。
ロゼレムしかないときは、児童思春期の神経発達症当事者には、粉砕して10分の1にしていたことなどがありましたが、それは図に示しましたように強さの差によるものです。
効能・効果
効能・効果は「小児期の神経発達症に伴う入眠困難の改善」となっています。
用法・用量
通常、小児では1日1回1mgを就寝前に内服する。なお、症状により適宜増減するが、1日1 回4mgを超えないこととなっています。
剤型
剤型は顆粒と1mg錠、2mg錠があります(図3)。
図3 メラトベルの剤型
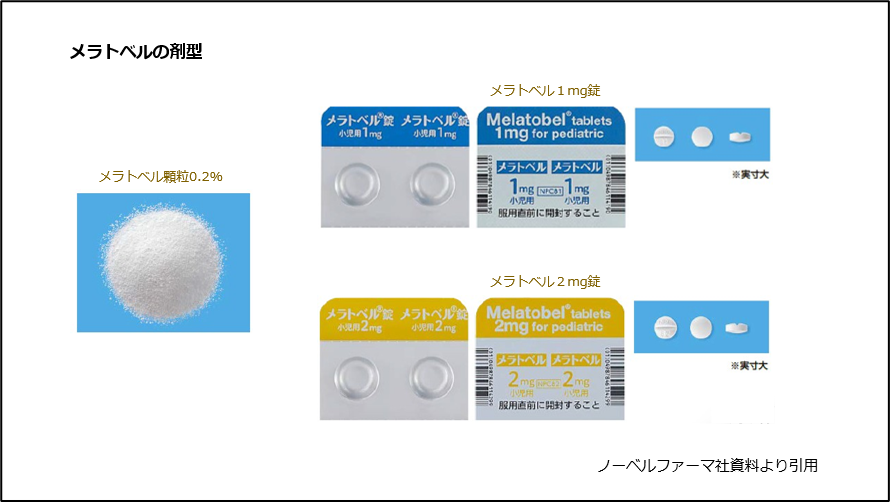
薬物動態
メラトベルを6歳から15歳の小児が、それぞれ0.8から3.3mgを内服した際、血中濃度は約20分で最高濃度に達し、約1.4時間後に半減します。
メラトベル1mgを成人が内服すると、血中濃度は約20分で最高濃度に達し、1.4時間後に半減します(図4)。
図4 メラトニン(メラトベル)の血中濃度の推移
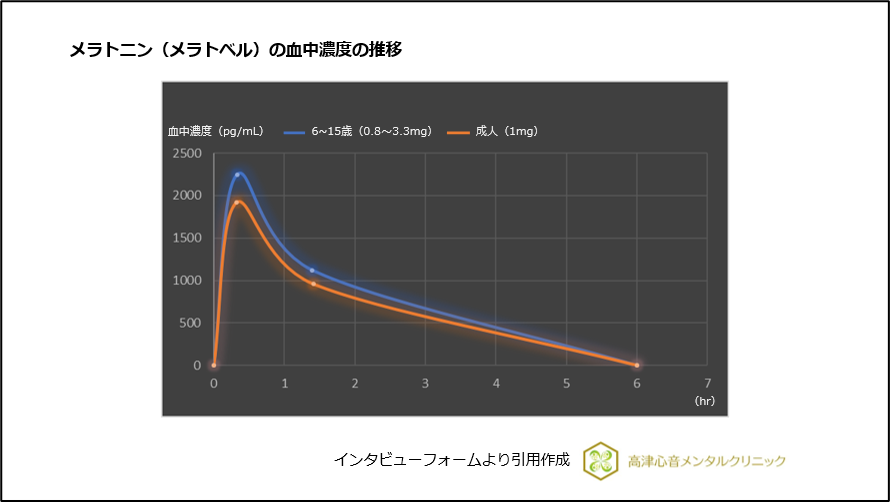
禁忌
禁忌として以下が設定されています。
- 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者さん
- フルボキサミンマレイン酸塩(ルボックス・デプロメール)を内服中の患者さん
フルボキサミンマレイン酸塩の禁忌は、フルボキサミンマレイン酸塩が、メラトベルを分解する酵素のCYP1A2の働きを阻害するため、メラトベルの血中濃度が上昇してしまうためです。
併用禁忌
併用禁忌として以下が挙げられています。
- CYP1A2阻害剤:
メラトベルの作用が強くあらわれます。
フルボキサミン(ルボックス・デプロメール)・シプロフロキサシン(シプロキサン) - カフェイン:
メラトベルの作用が強くあらわれます。 - 喫煙:
メラトベルの作用が低下します。
副作用
国内臨床試験における1%以上の副作用は以下でした。
- 傾眠(4.2%)
- 頭痛(2.6%)
- 肝機能検査値上昇(1.3%)
おひとりで悩んでいませんか?
まずはかかりつけ内科等で相談するのも1つの方法です。
文献
- 1) Comai S, et al.: Sleep-wake characterization of double MT₁/MT₂ receptor knockout mice and comparison with MT₁ and MT₂ receptor knockout mice. 243:231-8, 2013.
- 2) Pfeffer M, et al.: The endogenous melatonin (MT) signal facilitates reentrainment of the circadian system to light-induced phase advances by acting upon MT2 receptors. 29: 415-29, 2012.
- 3) Kato K, et al.: Neurochemical properties of ramelteon (TAK-375), a selective MT1/MT2 receptor agonist. Neuropharmacology, 48: 301-10, 2005.
- 4) Sugden D, et al.: Melatonin receptor pharmacology: toward subtype specificity. Biology of the Cell, 89: 531-537, 1997.
睡眠薬の関連コラム一覧
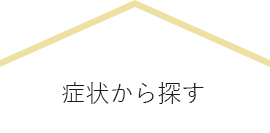
- 頭が働かない
- 寝つきが悪い
- やる気が起きない
- 不安で落ち着かない
- 朝寝坊が多い
- 人の視線が気になる
- 職場に行くと体調が悪くなる
- 電車やバスに乗ると息苦しくなる
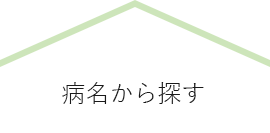
- うつ病
- 強迫性障害
- 頭痛
- 睡眠障害
- 社会不安障害
- PMDD(月経前不快気分障害)
- パニック障害
- 適応障害
- 過敏性腸症候群
- 心身症
- 心的外傷後ストレス障害
- 身体表現性障害
- 発達障害
- ADHD(注意欠如・多動症)
- 気象病・天気痛
- テクノストレス
- バーンアウト症候群
- ペットロス(症候群)
- 更年期障害
- 自律神経失調症